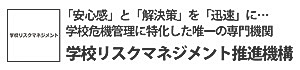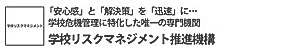学校以外が担う業務の盲点/ 鈴木彰典 元 校長
学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。
さて、経済協力開発機構(OECD)は、2024年度に実施した国際教員指導環境調査の結果を公表しました。それによりますと、日本の教員の仕事時間は1週あたり小学校52.1時間、中学校55.1時間と、いずれも世界最長でした。このような状況の中で、文部科学省は9月末に、教員の働き方改革を促す新しい指針を全国の自治体や教育委員会に通知しました。今号では、働き方改革を進める中で想定されるリスクについて、特に保護者対応に焦点を当ててお伝えいたします。
◆新しい「学校の働き方改革」の波
長年、教育現場では「教職員の多忙化」が深刻な課題とされてきました。授業準備・行事準備・生徒指導などに加え、保護者対応、地域連携、さらには危機対応まで担う状況が続き、教職員の精神的・時間的余裕は限界に達していました。
そのような中で、「学校以外が担う業務」の一つとして「保護者からの不当要求への対応」が示されたことは、現場の教職員にとって一定の救いと感じられる面もあります。これまで、学校は保護者からの強いクレームや過度な要求に頭を悩ませてきました。明確に「それは学校の責任範囲ではない」と線引きされることで、教職員の心理的負担が軽減されるのではないかという期待が高まっています。
しかし一方で、この方針の運用には慎重さが求められます。もし「保護者の不当要求には学校が関与しない」という形だけが先行すると、学校と家庭の間に「冷たい壁」が生まれ、信頼関係が損なわれるおそれがあるからです。
◆「不当要求」と「正当な訴え」の狭間で
ここで留意したいのは、「不当要求」と「正当な訴え」の線引きが容易ではないという点です。たとえば、保護者が子どもの安全確保を求めて訴えるケースも、教職員の立場からは「過度な要求」と受け止められることがあります。しかし、その背景には事故やトラブルを未然に防ぎたいという親心がある場合も少なくありません。
保護者が強く訴える背景には、「学校に話を聞いてもらえなかった」「不安が放置された」という感情が潜んでいることが少なくありません。たとえ対応の最終段階を外部機関に委ねるとしても、学校の初期対応としては、「事実確認」と「傾聴」が欠かせません。
学校現場として大切にしたいことは、
-
- 初期対応では「共感をもって話を聞く」
- 解決が難しい場合は「制度として外部機関につなぐ」ことを丁寧に説明する
- 「学校が拒否している」のではなく「適切な機関が対応する」仕組みであることを明確に伝える
というステップです。これらの基本を押さえておくことで、保護者との信頼を失うことなく、業務の適正な分担が可能になります。
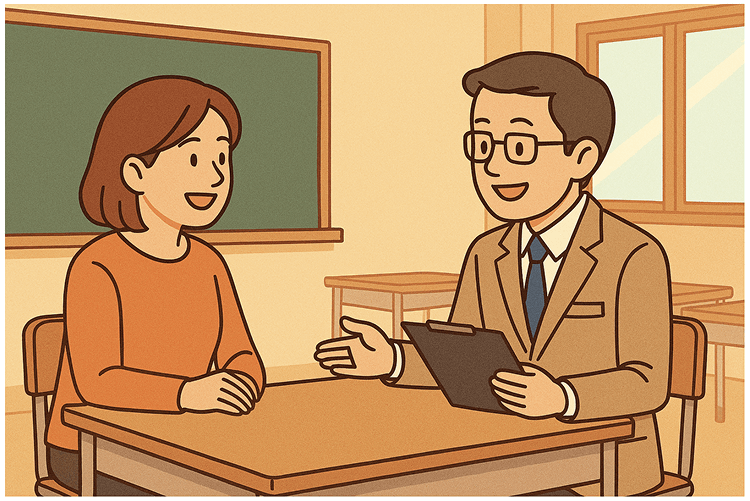
◆関係の断絶を防ぐコミュニケーション設計
近年、保護者から「以前より学校が冷たくなった」「きちんと対応してくれなくなった」といった声が聞かれることがあります。これは、教職員が意図的に拒んでいるわけではなく、時間的・精神的余裕のなさから、関わる力が弱まっている現実の表れです。
ここで危機管理上の課題となるのは、学校と家庭の関係の質が低下したときに、誤解や不信が生まれやすくなるという点です。
トラブルが起こった際に、日頃から信頼関係が構築されていれば冷静に話し合うことができます。しかし、関係が希薄な状態では、少しの行き違いが「学校の隠ぺい」「説明不足」と受け止められ、クレームにつながることがあります。
そのため、危機管理の視点からは“関係の量”と“関係の質”をどう確保するかが鍵となります。具体的には次のような取り組みが効果的です。
-
- 学校だよりや学校ホームページで、学校がどのような考え方で働き方改革に取り組んでいるかを定期的に発信する。
- 保護者会などで、「学校の対応範囲」と「外部機関の支援体制」を丁寧に説明する。
- 苦情や要望を受けた際は、誰が、どのように、どの程度対応するかを、学校全体で共有しておく。
◆「やめる改革」から「守る改革」へ
働き方改革は、業務量を減らすだけでは本質的な改革にはなりません。むしろ重要なのは、何をやめるかよりも、何を守るかを明確にすることです。学校の使命は、子どもたちの安全・成長・学びを守ることにあります。そのためには、教職員が安心して働き、子どもと向き合う時間を確保することが不可欠です。
その実現には、次の2つの視点が求められます。
1.学校の中でしかできない仕事に集中する
授業、生徒指導、安全確保など、子どもの成長に直結する仕事を優先し、他の業務は外部と協働して行う。
2.教職員がチームとして支え合う文化を育てる
個人の努力に依存するのではなく、学校全体で情報共有・相互支援を行う体制を構築する。
◆これからの学校に求められる危機管理力
今後、学校はますます「説明責任」と「信頼関係」の両立が問われる時代に入ります。保護者や地域との対話が減ることは、一見すると業務削減のように見えても、実は新たなリスクを生む可能性があります。そのリスクを防ぐ鍵は、情報公開・共有、そして対話の継続です。
危機管理の視点から言えば、トラブルの多くは「不適切な初期対応」と「説明不足」が発端です。どんなに小さな問題でも、
-
- 早い段階で情報を共有する
- 隠さずに事実を整理する
- 感情に寄り添いながら説明する
という姿勢が、信頼を守る最大の防波堤になります。それは、学校が「誠実に対応してくれる場所」であるという社会的信頼の礎でもあります。
◆おわりに
働き方改革は、単なる労務改善ではなく、学校の信頼を守る改革でもあります。教職員が心身の余裕を持って子どもに向き合えること、適切に外部と連携して保護者と良好な関係を築けること。これらがあって初めて、学校が「安全で安心できる学びの場」として機能します。
※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。
編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典