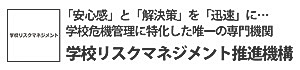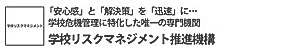学校教育の信頼回復に向けて/ 鈴木彰典 元 校長
学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。
近年、学校教育に対する信頼が揺らいでいます。教育現場では、子どもたちの健やかな成長を支えるため、日々真摯な努力が積み重ねられています。しかし、一方で一部の教職員による不祥事(体罰、暴言、盗撮、性加害など)が相次いで報道され、教育に携わる多くの教職員の献身的な取り組みが一瞬でかき消されてしまう現実があります。
こうした状況を憂慮しつつも、悲観にとどまってはいけません。むしろ、危機を契機として学校教育を再生させる取り組みを進めることが求められています。今号では、信頼回復に向けて教育現場が取り組むべき視点と具体的方策について、情報提供いたします。
◆信頼失墜と現状の課題
まず、学校教育に対する信頼が低下している背景を冷静に捉える必要があります。
(1)不祥事の連鎖的影響
教職員による不適切な行為は、一件の事案であっても社会に大きな衝撃を与えます。報道を通じて瞬時に拡散され、「また学校か」という印象を世間に与えてしまうことが少なくありません。多くの教職員が真面目に教育活動に取り組んでいるにもかかわらず、一部の行為によって学校全体への不信感が拡大してしまう点が最大の課題です。
(2)説明責任の不足
不祥事が発生した際、学校が説明を遅らせたり、部分的にしか公表しなかったりすると、「隠蔽しているのではないか」という疑念が生じます。信頼をさらに失わせる要因は、その後の不適切な対応である場合も少なくありません。
◆信頼回復に必要な視点
信頼を回復するためには、以下の四つの柱を意識することが重要です。
(1)透明性と説明責任の徹底
不祥事が発生したときに、最も重要なことは、隠さず誠実に説明する姿勢です。
①迅速な情報公開
事実関係を確認した上で、可能な範囲で速やかに保護者や地域に説明することが欠かせません。遅延や矛盾はさらなる不信感を招きます。
②説明の一貫性
誰がどの立場で説明するかを事前に定め、学校としての方針を明確にする必要があります。その際、学校に過度な負担を掛けないよう配慮することも大切です。
③情報の共有
学校内部でも、教職員全員に正確な情報を共有し、誤解や噂が広がらないように努めることが求められます。
(2)倫理と意識改革
教職員一人ひとりの倫理観が学校教育を支えます。
①定期的な倫理研修
体罰やハラスメント、SNS利用に関するトラブルなど、具体的な事例を取り上げて議論することが効果的です。年に数回の形式的な研修ではなく、日常業務に直結する形での継続的な研修が望まれます。
②リスクセンスの向上
危険なことを危険なこととして認識できる力をリスクセンスと呼びます。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、重大な不祥事につながります。小さな兆候やリスクに敏感になり、早期に対応する習慣を養う必要があります。
③相談文化の醸成
悩みを抱え込まず、同僚や管理職に相談できる環境を整えることが重要です。「弱さを見せてもよい」という職場風土が、不祥事の予防につながります。
(3)学校文化の再構築
信頼回復には、日々の教育活動そのものが「信頼を積み重ねる営み」となる必要があります。
①保護者との対話
定期的な懇談会やアンケートなどを通じて収集した意見を学校運営に反映させることで、共に教育を支える意識が生まれます。
②地域との協働
地域人材の活用や地域行事への参加など、地域社会と一体となった学校づくりを推進することで、外部からの視点が学校の健全性を保つことにつながります。
③ポジティブな発信
不祥事の影に隠れがちな教育現場の前向きな取り組みを積極的に発信することも大切です。教育活動の成果や子どもたちの成長を共有することが、信頼を回復する一歩となります。
(4)継続的な改善努力と長期的視点
信頼は短期間で取り戻せるものではありません。重要なのは「継続と一貫性」です。
①仕組みの定着
研修やチェック体制を一時的なものにせず、数年単位で継続することが大切です。
②外部評価の活用
第三者による評価や監査を取り入れることで、客観性を確保できます。
③進捗の可視化
改善の取り組みを定期的に発信し、「学校が変わろうとしている姿勢」を示すことが、信頼回復につながります。

◆おわりに
教育の本質は、子どもたち一人ひとりの成長を支えることにあります。教職員の不祥事はその大切な営みを揺るがすものですが、そこから学び、より強固な教育基盤を築くことができます。
信頼を取り戻す道は平坦ではありません。しかし、全国の教職員一人ひとりが「子どもたちのために」という原点を胸に刻み、共に歩みを進めるならば、学校教育への信頼は必ず回復し、さらなる発展へとつながっていくことでしょう。
当機構は、今月で創業21年目を迎えました。これからも、全国の学校(園)運営を支えるとともに、学校(園)の信頼回復を図るため、学校(園)トラブルの支援に引き続き尽力してまいります。何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
|
【10月】教師になった日の初心を胸に、子どもたちの顔を見る と、あの頃の情熱がよみがえります。伝えるべきことをまっすぐに語り、分かりやすく解説し、自らやってみせることに全力を注いでいた日々。私たちは子どもの心に火を灯し、好奇心を育みながら、彼らが未来を切り拓く力を信じて支える教師になりたいものです。 |
※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。
編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典