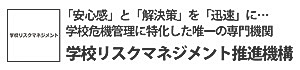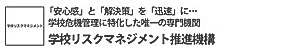子どもたちを性犯罪から守るために ~日本版DBS制度の導入~ / 鈴木彰典 元 校長
学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。
近年、教職員による児童生徒へのわいせつ・性犯罪が後を絶たず、教育現場の信頼が大きく揺らいでいます。ニュースでは、懲戒免職となった教員が他の自治体や私立学校に再就職していた事例も報じられ、全国の教育機関に衝撃を与えました。今号では、子どもたちをわいせつ・性犯罪から守るために導入される、日本版DBS制度の背景や活用方法、制度運用に伴う課題などについてお伝えします。
◆DBS制度とは何か?
DBSとは、児童生徒などの保護対象者に対する性犯罪歴等を事前に確認する制度です。この制度は、イギリスで2002年に発生した少女殺害事件を契機に創設されました。イギリス版DBSでは、保育士や教職員など、子どもや弱者と接する職に就く者について、警察の保有する性犯罪歴を雇用前に照会し、適格性を審査します。一定の基準に該当する者については、就労が禁止される就労制限処分が下され、社会全体で子どもを守る枠組みが構築されました。
◆日本版DBS制度の創設へ
~どのような背景があるのか?~
1.教育現場の現実
文部科学省の発表によると、わいせつ行為等による懲戒処分者の数は年々増加しており、2023年度の公立学校教職員のわいせつ行為等による懲戒処分者は320名となり、過去最多を記録しています。しかも、その中には児童生徒への直接的な行為だけではなく、SNSを通じた不適切な接触や、盗撮・盗品の所持なども含まれています。
2.制度化への機運
このような状況を受けて、政府は2024年に「日本版DBS制度」創設に向けた法制度整備を閣議で決定し、2025年度から一部施行される見通しとなりました。これにより、教員採用時などに性犯罪歴等を照会し、必要に応じて採用拒否や職場からの排除を可能とする法的な枠組みが整備されつつあります。
◆日本版DBS制度の仕組みと対象
1.対象となる職種
・教職員(国公私立)
・保育士・学童指導員
・医療機関で子どもに接する職種
・スポーツクラブ・習い事・学習塾の講師など
2.照会内容と対象者
制度では、雇用前に都道府県や内閣府などを通じて、「性犯罪歴の有無」を確認できるようにする仕組みが整備されます。照会の対象となるのは、以下のような犯罪歴のある者です。
・強制性交罪、強制わいせつ罪など重大な性犯罪
・児童買春・児童ポルノ禁止法違反
・児童福祉法違反(淫行誘引等)など
このような前科・前歴を有する者について、採用を拒否したり、既に雇用されている場合には職務から外したりすることが可能となります。

◆教育現場での活用の意義と効果
1.採用時のフィルター機能
新任教員の採用に際し、性犯罪歴の有無を確認することで、子どもたちを性犯罪者から未然に守ることが可能になります。これまでは履歴書や面接では把握しきれなかった過去の経歴について、制度的に確認できるようになる点は非常に大きな前進です。
2.職場内での安心感の向上
制度の存在により、児童生徒はもちろん、同僚教職員や保護者にも安心感を与えることができます。「学校は安全な場所である」と思われる風土を醸成する制度です。
3.早期の再発防止につながる
過去に性犯罪歴がある者の再犯率は高い傾向があるとされており、制度により高リスク者を現場から排除することは極めて合理的な対応といえます。
◆制度運用における課題と今後の論点
1.対象犯罪の範囲の限定性
「下着の窃盗」「ストーカー規制法違反」など、刑法上は性犯罪とされない場合が多く、制度の対象から漏れる可能性があります。しかし、これらの行為も再犯リスクが高く、子どもへの被害につながりうるため、制度の見直しや対象拡大の検討が必要です。
2.プライバシー保護とのバランス
前科・前歴という極めてセンシティブな情報を取り扱うことから、個人の人権と社会的な利益のバランスをどう取るかは大きな論点です。制度が恣意的に運用されないよう、厳格な基準や透明性の高い審査体制が求められます。
3.現場の事務負担
DBS照会の申請・管理は、教育委員会や学校法人の新たな事務負担になる可能性があります。研修や支援ツールの整備、外部機関との連携体制が不可欠です。
◆制度を活かす視点が大切
日本版DBS制度は、子どもたちを守るための重要なセーフティーネットです。しかし、制度だけで全てを防げるわけではありません。教職員は、日常的に子どもたちの変化に気づき、不適切な言動や兆候に敏感であること、通報や相談の体制を整えておくことが不可欠です。
また、同僚教職員が不適切な行動を取った場合、見て見ぬふりをしない勇気と組織風土を育むことが、子どもを守る教育現場につながります。
◆おわりに
今、学校教育は一部の教職員の不適切な行為等により、児童生徒、保護者、地域の方々からの信頼を失いかけている状況にあります。信頼回復を図ることは容易なことではありませんが、皆さんの英知を結集して乗り越えていきましょう。当機構も皆さんのお力になれるよう、これからも尽力いたしますので、よろしくお願いいたします。
|
須佐之男命が八岐大蛇を退治し、奇稲田姫を救った神話には、大切な何かを守ろうとする強い意思が描かれています。現代の学校でも、保護者対応などに心を痛める先生がたくさんいます。誰かが悪いわけではなくても、責任を背負い込んでしまう。そんな先生たちをそっと支えるような、知恵や優しさを伝える物語が、今こそ必要なのかもしれません。 |
※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。
編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典