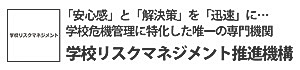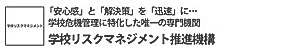学校(園)の信頼を守るために~ガバナンスと説明責任を~/ 鈴木彰典 元 校長
学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。
近年、全国各地で教職員による不祥事や教育現場での対応の不備が報道されるたびに、学校(園)教育に対する信頼が失われていきます。ひとたび不適切な対応や不誠実な情報開示があれば、保護者や地域住民の不信感は一気に高まり、学校(園)への厳しい批判が巻き起こります。こうした事態は、関係する児童生徒等の心にも影を落とし、教育の営み自体が停滞するリスクをはらんでいます。今号では、現在学校(園)に求められている対応についてお伝えします。
◆「ガバナンス」と「説明責任」の重要性
ガバナンス(統治機構)とは、組織の意思決定の透明性や健全性を保ち、組織の内外から信頼を得るための仕組みを指します。例えば、方針を定め、規則をつくり、それを守り、守らせて不備を改善していくことです。学校(園)においては、校(園)長を中心とした組織運営に限らず、すべての教職員がガバナンスの担い手であるという意識が欠かせません。
一方、説明責任とは、保護者・地域・児童生徒・行政など、学校(園)が関わる全ての関係者に対し、教育活動の目標や成果などについて、わかりやすく丁寧に説明する責任を指します。何か問題が起きたときだけでなく、日常的な情報共有や姿勢そのものが問われています。
◆初動対応の遅れと情報隠蔽が信頼を失墜
不祥事やトラブル、事故が発生した際に最も重要なことは、「正確で迅速な初動対応」と「誠実な情報開示」です。
近年の報道では、事件そのものよりも、その後の学校(園)の対応に非難が集まるケースが目立っています。特に初期段階での不適切な判断や説明の誤りが、結果として大きな不信と混乱を招く原因となっています。
例えば、教職員の不祥事が発覚した際、「関係者のプライバシーに配慮して情報を伏せた」という判断が、外部からは「隠蔽体質」と受け取られることもあります。情報公開には一定の慎重さが求められますが、学校(園)として「何をどう伝えるか」「どこまで開示するか」といった判断基準と手順を、日頃から整理し、意思決定の軸がぶれないようにしておく必要があります。
◆危機発生後の対応は信頼回復の鍵
マスコミへの対応、保護者説明会の実施、SNS上での誤情報への対処など、危機発生後の対応も学校(園)の重要な役割のひとつです。多くの学校(園)では、管理職に任せきりにしていることが少なくありませんが、対応方針を定めたうえで、教職員全員がその一部を担うことが大切です。
保護者説明会では、事実関係の説明に加え、「原因」や「再発防止策」についても丁寧に伝える必要があります。また、SNSの情報拡散力を過小評価してはいけません。誤情報や一部の声が急速に広がり、二次被害を生むことがあります。
学校(園)としての公式の情報発信ルート(ホームページ、メール連絡、文書など)を日頃から整備、周知しておくことで、いざという時の情報混乱を最小限に抑えることができます。
◆教職員一人一人に求められる役割と責任
学校(園)組織の信頼は、校(園)長一人のリーダーシップだけでは保てません。すべての教職員が「自分は学校(園)の顔である」という自覚を持ち、行動することが極めて重要です。
例えば、あるクラスでの問題行動やトラブルを担任だけで抱え込んでしまうと、対応が遅れたり、判断を誤ったりする可能性があります。こうした事態を防ぐためには、学校(園)全体での情報共有、報告・連絡・相談(いわゆる「ホウ・レン・ソウ」)の徹底が不可欠です。
また、自らの不注意によってトラブルが発生した場合でも、隠すことなく正直に報告し、組織として対応を協議する姿勢が求められます。自分の判断や行動が、学校(園)全体の信頼に直結するという意識を持つことが大切です。
◆信頼は日々の積み重ねから構築される
学校(園)への信頼は一朝一夕には築かれません。日頃からの丁寧な保護者対応や地域とのコミュニケーション、オープンな学校(園)運営が、いざという時の支えになります。
例えば、日常的に学校(園)だよりや学級通信で教育活動の様子を発信していれば、保護者の理解と関心も深まり、万が一トラブルが起こっても「まず学校(園)の話を聞こう」と思ってもらえる可能性が高まります。
また、学校(園)の公開日や地域行事への参加、学校(園)評価アンケートの実施などを通じて、関係者や地域住民との接点を増やすことも信頼構築につながります。

◆おわりに
学校(園)の信頼は、制度や設備だけでは守れません。それを支えているのは、教育現場で子どもたちと向き合う教職員一人一人の姿勢と言動です。日々の誠実な実践と、一つ一つの判断・行動の積み重ねこそが、学校(園)全体の信頼を形づくっていきます。
「自分一人くらい大丈夫だろう」「これは管理職の仕事だ」という意識を改め、教職員全員がガバナンスと説明責任の一翼を担っているという覚悟を持って、日々の教育活動にあたっていきましょう。
その先に、子どもたちの安心、保護者の納得、地域の支援、そして何より、教育への確かな信頼が育まれていくはずです。
当機構は、これからも全国の学校(園)の信頼を守るため、学校(園)トラブルの支援に引き続き尽力してまいります。何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
|
「誠心誠意」:理性と感情のバランスを保ちながら、日々刻々と変化する出来事に向き合っている先生方。忙しさに追われ、心のゆとりを失いそうになることもあるでしょう。そんな時、ふと立ち止まり、自分自身を顧みる瞬間が生まれます。それは、誰もが経験することではないでしょうか。最後に人の心を動かすのは、「まごころ」だと信じています。 |
※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。
編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典