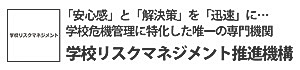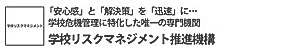夏休みを前に危機感を持つ / 鈴木彰典 元 校長
学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。
さて、1学期もまもなく終了を迎え、夏休みが目前になってきました。しかし、教職員の皆様にとって、夏休みは子どもたちの心身の安全に一層注意を払うべき時期でもあります。今号では、最近の傾向とともに、どのような取り組みが求められているのかをお伝えいたします。
◆増加傾向にある少年犯罪・非行
~背景に潜むSNSと仲間意識~
1.SNS発信型の非行問題
ここ数年で顕著になってきたのが、「SNS映え」を狙った非行問題の増加です。公共の場での迷惑行為や破壊行動を動画撮影し、それをSNSに投稿することで“注目されたい”という心理が働くケースが増えています。こうした行動の背景には、自己承認欲求や仲間との一体感、あるいは匿名性による気軽さなどがあり、単なる悪ふざけでは済まされない事態を引き起こすこともあります。子どもたちは、こうした投稿が一度インターネット(以下、ネット)に載ると完全には消せないこと、その結果として将来の進学や就職にも影響を及ぼしかねないことを、十分に理解していません。また、投稿を煽るようなコメントによって、さらに過激な行動へとエスカレートする危険性もあります。
2.オンラインの交友からオンラインのトラブルへ
SNSやオンラインゲームを通じて出会った相手と直接会う、いわゆる「オフ会」や「リアル出会い」は、性被害や金銭的なトラブル、暴力事件などにつながることも少なくありません。とくに思春期の子どもは、「誰かとつながりたい」という気持ちが強く働き、注意喚起だけでは防止しきれない場合があります。
◆夏休みに増えるリスク
~自由時間の落とし穴~
1.深夜徘徊・無断外出
長期休業中は生活リズムが崩れやすく、夜型生活に傾きがちです。その結果、夜間に友人と出かけたり、保護者に無断で外泊したりといった行動が見られるようになります。こうした行動は、犯罪に巻き込まれるリスクを高め、場合によっては加害側になることもあります。
2.ゲーム・スマホ依存と課金トラブル
スマートフォンやゲームへの依存もまた、夏休みに起こりやすい問題の一つです。特にオンラインゲームや動画配信サービスは、長時間使用や高額課金などの問題を引き起こしやすく、家庭内でのトラブルや金銭被害につながる恐れがあります。
◆夏休み明けに懸念される自殺・不登校
夏休み明けの8月下旬から9月上旬にかけては、子どもたちの自殺件数が年間で最も多くなる傾向にあります。新学期の始まりが、子どもたちにとって非常に大きな心理的ストレスになっていることを表しています。
また、夏休みをきっかけに不登校になる児童生徒も少なくありません。生活リズムが乱れることで登校が億劫になったり、学校に戻る理由が見つからないと感じたりすることが、不登校の要因の一つになります。

◆少年少女が事件などに巻き込まれた事例
- 動画共有アプリに投稿していた10代女子は、小学生になりすました男から言葉巧みにだまされ、わいせつな自画撮り画像を送信させられた。
- 深夜徘徊や家出をしていた少年少女が、新宿区歌舞伎町の“トー横”と呼ばれるエリアで喫煙、飲酒、オーバードーズなどの疑いで補導された。
- 男子小学生が、家族のスマートフォンを使用してオンラインゲームに約10万円を課金した。
- 自殺願望者としてSNSに投稿した女子高校生が言葉巧みに誘われ、練炭自殺させられた。
◆子どもたちを守るための予防策
1.学校でできること
①夏休み前の啓発指導
学年集会・学級活動を通して、「夏休みの生活 で守るべきルール」「SNS・スマホ利用の注意点」「困ったときの相談先」を具体的に指導する。
②児童生徒の“変化”や“前兆”に気づく工夫
事前アンケートや個別面談を実施し、悩みを抱えている児童生徒を早期に把握する。必要に応じてスクールカウンセラーや養護教諭とも連携する。
③休業中のフォロー体制の整備
夏休み期間中も「相談窓口」を確保し、緊急時には保護者や児童生徒が学校に連絡できる体制を周知する。
2.家庭でできること
①家庭内のルールの明確化
スマートフォンの使用時間、外出時間、食事や就寝時刻など、基本的な生活ルールを子どもと話し合って決める。また、ネットによるトラブルを防止するために、「ネットで嫌なことがあったら、すぐに保護者に知らせる」「ネットで知り合った人と勝手に会わない」「ネットで有料サービスを利用したときは保護者に相談する」などのルールを決める。
②子どもの“小さな変化”を見逃がさない
言葉数が減った、感情の起伏が激しい、外出を極端に嫌がる――そんな変化が見られたら、早めに学校や専門機関に相談する。
③保護者自身が情報を得る意識を持つ
ネットリスクや少年非行の最新情報を知ることで、子どもへの理解が深まる。教育委員会や警察などの関係機関が発行する啓発資料などを活用していただく。
◆おわりに
子どもたちが夏休みを安全・健全に過ごすことは、私たち大人の共通の願いです。そしてその実現には、学校と家庭が同じ方向を向きながら連携し合うことが欠かせません。この夏、子どもたちの成長を願い、心身ともに豊かな経験を積めるよう、私たちができることに取り組んでいきましょう。
|
「できるかも」:一度失敗すると、再び挑戦するには勇気が必要。特に、叱られると自信を失う。誰かに代わりにやってもらってできても、本当の自信にはつながらない。「できないこと」は、やり方を工夫することで「できる」ようになる。「できた」という成功体験を積み重ね、自己肯定感を高め、自信を育みたい。その自信が、他のことも「できるかも」という未来への大切な一歩となる。 |
※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。
編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典