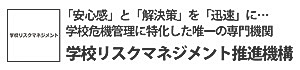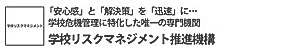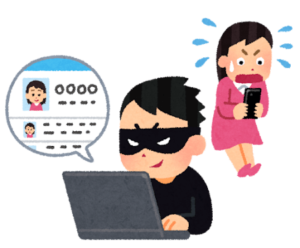
未成年者とSNSの危険性 / 鈴木彰典 元 校長
学校リスクマネジメント推進機構の鈴木彰典です。私は過去に校長経験が13年あり、マスコミが注目していた教育困難校の立て直しを任されてきた経歴もございます。このような学校では報道される内容と実情が全く異なることもあるのですが、様々な経験が今の学校現場の支援に活かされていると感じております。
近年、未成年者がSNSを通じて犯罪に巻き込まれたり、いじめに関与したりする事例が増えています。このような状況に対応するためには、児童生徒等がSNSのリスクを正しく理解し、安全に利用できる能力を身につけることが不可欠です。今号では、SNSに潜む危険性を踏まえ、学校で実施すべき情報リテラシー教育の重要性と具体的な取り組みについて、ご紹介します。
◆SNSを利用した犯罪の防止
①闇バイトの危険性と未成年者の加担
SNS上で「簡単に稼げる高額バイト」と称して違法行為に関与させるケースが増加しています。特に、犯罪グループが未成年者をターゲットにし、違法な仕事を紹介する事例が多く起きています。例えば、ATMからの不正送金の受け子や、違法薬物の運搬、さらには強盗事件への関与が問題になっています。これらの犯罪は「楽に稼げる」と思わせる手口が多く、未成年者が安易に関わるケースが後を絶ちません。
②性犯罪被害のリスクと防止策
SNSを通じて未成年者が性犯罪の被害に遭うケースも増加しています。特に、出会い系アプリやSNSを介して知り合った相手から性被害を受ける事例が多発しています。加害者は巧妙な手口で未成年者に接触し、最初は親しげに接しながら信頼を得た後、脅迫や金銭の要求を行うことがあります。未成年者は「自分は大丈夫」と思いがちですが、被害に遭うと深刻な精神的ダメージを受け、相談できずに苦しむケースが多いです。
③教育現場での具体的な取り組み
闇バイトや性犯罪に未成年者が巻き込まれないために、学校では以下のような取り組みが効果的です。
(1)事例をもとにディスカッションの実施
実際の犯罪事例を教材として用い、「SNS上で怪しいバイトの募集を見たらどう対応すべきか?」などをグループで議論させることで、危機意識を持たせることができます。
(2)ロールプレイを取り入れた授業
教員が「闇バイトの勧誘者」役を演じ、生徒・学生がどのように対応するかを考える場を設けることで、具体的な対応方法を学ばせることができます。
(3)警察や専門家による講演会の開催
地域の警察署と連携し、SNS犯罪の最新手口や対策について講演を行うことで、より現実に即した学びの機会を提供することができます。
◆誤情報やフェイクニュースの見極め方
①SNS上の誤情報の拡散や影響
SNSでは、真実ではない情報が拡散されることが多くあります。特に、誇張された情報やセンセーショナルな見出しのニュースは拡散されやすく、未成年者は影響を受けることがあります。例えば、特定の芸能人に関するデマや、社会問題に関する誤った情報などがSNSで拡散されることがあります。誤情報を信じて行動すると、不必要な不安を抱えたり、間違った判断をしてしまうリスクがあります。

②教育現場での具体的な取り組み
学校では、以下のような取り組みが効果的です。
(1)教員自身のリテラシーの向上
誤情報やフェイクニュースの見極め方を学び、情報の信憑性を確認する習慣をつけることが重要です。そのためにも、定期的な研修やワークショップを通じて、実戦的なスキルを磨くと良いと思います。
(2)フェイクニュースを見破るワークショップの実施
実際のニュース記事をいくつか用意し、「本物」「誤情報」「フェイクニュース」のどれかを児童生徒等に見極めさせる活動を行うと、見破る力を身につけることができるようになります。
(3)情報源の信頼性を調べる課題の実施
「〇〇という情報をSNSで見たら、それが本当かどうか調べてみよう」という課題を出し、情報の裏を取る練習を通じて、情報源を確認する習慣を身につけることができます。
(4)AIを使ったフェイク画像の検証
生成AIによるフェイク画像を見せ、「本物と偽物の違い」を考えさせることで、画像や動画が簡単に操作できることを学べます。
◆SNSいじめの防止と対応策
①SNS上でのいじめの現状
SNSを介したいじめ、いわゆる「ネットいじめ」は、従来の対面でのいじめとは異なり、匿名性や拡散性、24時間続くという特徴があります。このことにより、被害者は逃げ場を失い、深刻な精神的ダメージを受けることが多くなっています。具体的な事例には、次のようなことがあります。
(1)クラスメートがSNS上で、特定の生徒の悪口を投稿し、それが瞬く間に拡散されました。被害生徒は学校内での人間関係に支障をきたし、登校できなくなりました。
(2)無料通話アプリのグループチャット内で、特定の生徒だけが意図的に無視されることが行われました。被害生徒は孤立感を深め、精神的に不安定になり、リストカットやオーバードーズを行うようになりました。
(3)SNSに投稿した自身の写真や個人情報が第三者に悪用され、画像掲示板に無断で掲載される被害が発生しました。被害児童に嫌がらせの電話や不審者の出没など、二次被害が生じました。
②教育現場での具体的な取り組み
学校では、以下のような取り組みが効果的です。
(1)「傍観者」にならないためのロールプレイの実施
いじめの現場を目撃したとき、どう行動すべきかを考えさせることで、被害者の心情を受け止め、いじめが深刻にならないようにする姿勢を育てることができます。
(2)投稿内容の影響を可視化する授業の実施
SNS上での「軽い気持ちの投稿」がどれほど大きな影響を与えるかを、実際の事例をもとに考えさせることで、いじめを防止する意識を高めることができるようになります。
(3)相談先の周知
学校の相談窓口、公的機関や民間の相談窓口などを紹介し、「助けを求める手段がある」ことを伝えることで、児童生徒等が孤立することを防ぐことができるようになります。
SNS上でのいじめは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすため、早期発見と適切な対応が求められます。学校、家庭、関係機関が連携し、児童生徒等が安心して生活できる環境づくりを進めていくことが重要です。
当機構にも、SNSを介したトラブルのご相談が寄せられます。トラブルの内容はさまざまですが、適切に対応しないと問題解決までに多くの時間を要してしまいます。そのためにも、家庭や関係機関と連携しながら情報リテラシー教育の充実に努めていただければと思います。
※この記事は当機構が制作・発行している「学校リスクマネジメント通信」をWEB版として編集したものです。
編集者 元公立小学校・中学校 校長 鈴木彰典